遺言事例集
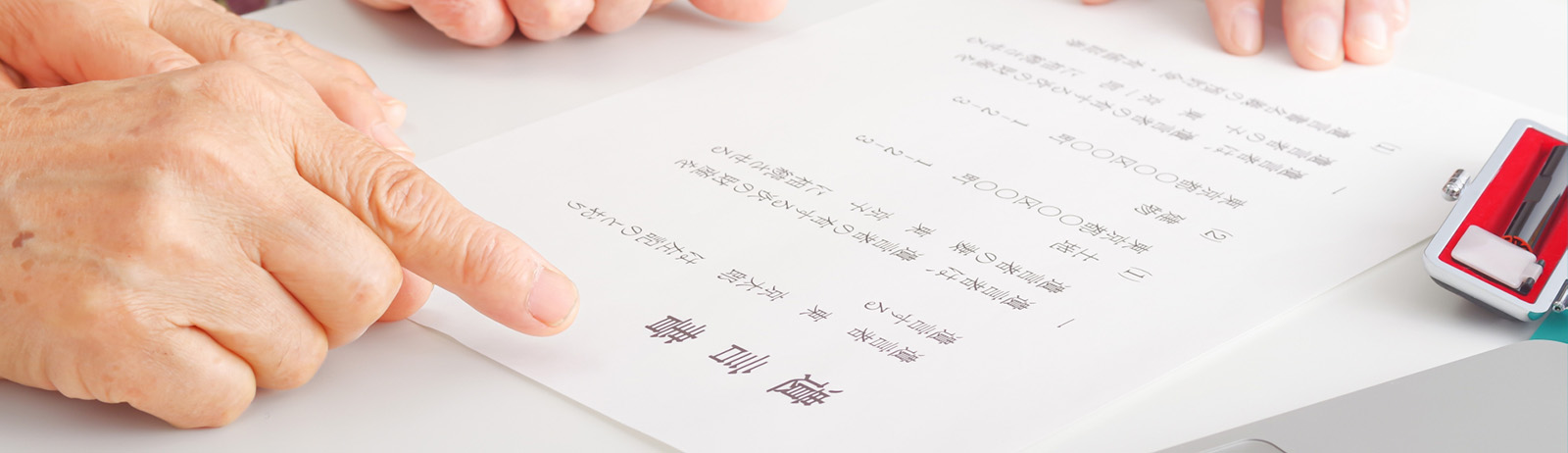
自宅の承継者、お墓などの祭祀財産の承継者を決めておきたい方
事例設定
- 甲野太郎さんには、妻と子3人(長男・二男・長女)がおり、現在、家族の中は至って円満である。
- 太郎さんは、曽祖父の代から引き継がれた自宅の土地家屋、先祖代々の墓や仏壇等を、同居する長男に引き継がせ、甲野家を承継してほしいと考えている。
遺言がない場合の懸念点
- 財産は、相続人全員による遺産分割協議によって承継者が決まるので、必ずしも自宅に住んでいる人が自宅の名義を取得できるとは限らない。
- お墓などの祭祀財産は、慣習で承継者が決まるとされているため、引き継がせたいと思っている人に引き継がせることができない場合がある。
本事例の解決策
- 遺産分割協議が不要になるので、住んでいる人に自宅を相続させることができる。
- 遺言で祭祀主宰者を指定した場合には、その者に承継させることができる。
事務所紹介
当事務所は、お客様に「パートナーズに頼めば安⼼」と⾔ってもらえることを成果と考えて、法的⼿続きの「分かりにくいを分かりやすく」お伝えしサービスを提供することをモットーにしています。皆さんにとって縁遠い存在であろう「司法書⼠」を⾝近に感じていただけるよう、明るくオープンな事務所を⽬指して、アクセスしやすい場所で路⾯店型の事務所を構え、スタッフも親切丁寧な対応を⼼がけ笑顔でご対応致します。
お客様との⾯談は個別ブースで⾏い、プライバシーを確保しております。また、作成費⽤についても必ず事前に御⾒積額をお伝えし、お客様に納得いただいてから委任契約を締結させていただいております。どうぞ安⼼してお気軽にご相談ください。
川越事務所
営業時間 ⽉〜⼟曜⽇ 9:00〜19:00
定休⽇ ⽇曜・祝⽇
※⽇曜・祝⽇時間外も事前にご予約いただければご対応いたします。
FAX:049-245-7933
住所 〒350-1123 埼⽟県川越市脇⽥本町29番地1
狭⼭事務所
営業時間 ⽉〜⾦曜⽇ 8:30~18:00
定休⽇ 土曜・⽇曜・祝⽇
※⼟⽇・祝⽇時間外も事前にご予約いただければご対応いたします。
FAX:04-2954-5899
住所 〒350-1305 埼⽟県狭⼭市⼊間川1丁⽬20番16号
無料相談をいつでも
承っております
お客様にとって、最善の解決策をご提案いたします。お気軽にお問い合わせください。
FAX:049-245-7933













